 ヨシボウ
ヨシボウこんにちは!
ヨシボウです
本記事では、日本の名著『歎異抄(たんにしょう)』に込められた親鸞聖人の「他力(たりき)」の思想について深く掘り下げていきたいと思います。
「他力」と聞くと、なんだか難しそうだな、と感じる人もいるかもしれません。
また、自分とは関係のない遠い世界の教えだ、と思う人もいるかもしれませんね。
でも、安心してください。
仏教の専門用語を避け、みなさんの日常生活に寄り添う形で、この深遠な教えを分かりやすく解説していきます。
『歎異抄』は、親鸞聖人が直接語られた言葉を、弟子の唯円(ゆいえん)が記録した書物です。
その中核をなすのが、「他力」の思想。
この「他力」こそが、現代を生きる私たちに、日々の苦悩を乗り越え、心穏やかに生きるための大きなヒントを与えてくれると、ぼくは考えています。
この記事を読み終える頃には、きっと「他力」という言葉が、みなさんの心に温かい光を灯してくれるはずです。
それでは、はじめていきましょう。


- 浄土真宗本願寺派の現役僧侶
- ブログ歴4年、5サイトを運営
- 趣味はブログと読書と朝活
- マインドフルネススペシャリスト資格所持
親鸞聖人が説いた「他力」とは何か?


まずはじめに、「他力」とは具体的に何を指すのでしょうか。
浄土真宗における「他力」とは、阿弥陀如来(あみだにょらい)の「本願(ほんがん)」、つまり「すべての人を救いたい」という大いなる願いと、その願いを実現するための「はたらき」を指す言葉です。
私たちは日常生活の中で、「自分の力で頑張る」という「自力(じりき)」の考え方に慣れ親しんでいます。
仕事も勉強も、人間関係も、すべて自分の努力次第だと教えられてきました。
もちろん、自力で頑張ることは素晴らしいことです。目標に向かって努力し、それを達成したときの喜びは、何物にも代えがたいものです。
しかし、親鸞聖人は、どんなに頑張っても、私たち人間にはどうしても乗り越えられない限界があることを見抜いていました。
たとえば、誰もが経験する「死」という避けられない現実。
どれだけ努力しても、私たちは死を避けることはできません。
また、誰もが抱える「煩悩(ぼんのう)」という心の苦しみ。 欲望、怒り、愚痴など、私たちは煩悩にまみれて生きているのが現実です。
自分の力だけで、これらの根本的な苦しみから完全に解放されることは、極めて難しいことなのです。
だからこそ、親鸞聖人は「他力」の教えを説かれました。
阿弥陀如来は、そんな「煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)」である私たちを、そのままの姿で救い取りたいと願われているのです。 これが、「他力」の根本的な意味合いです。
「自力」と「他力」の間に立つ私たち


ぼくたちは、普段の生活の中で、無意識のうちに「自力」に頼って生きています。
たとえば、朝起きて会社に行くこと、食事をすること、誰かと会話をすること。
すべて自分の意思で、自分の力で行っているように感じますよね。
しかし、少し立ち止まって考えてみてください。
私たちは、自分の力だけで生きているのでしょうか?
朝、目覚めるのは、太陽が昇り、地球が自転しているからです。
食事をするのは、誰かが育ててくれた食材があり、それを調理する人がいるからです。
誰かと会話ができるのは、言葉という共通の認識があり、相手が話を聞いてくれるからです。
私たちは、無数の「縁(えん)」によって生かされていますよね。
他者との関係性、自然の恵み、社会の仕組み。これらすべてが、私たちの存在を支えているのです。
親鸞聖人は、このことを「宿業(しゅくごう)」という言葉でも表現しています。
過去の行いや、様々な縁が、今の私たちの状態を形作っているという考えです。
自分の意思だけではどうにもならないことがある、という事実を受け入れることが、「他力」への第一歩と言えるでしょう。
「他力」とは、決して「何もしない」ということではありません。
自分の力の限界を知り、それでもどうにもならないことを、阿弥陀如来の大いなるはたらきにゆだねる、という心の姿勢なのです。
「他力」の思想が現代人に与える救い


現代社会は、とかく「自己責任」が問われる時代です。
「頑張れば報われる」「努力が足りない」といった言葉が、私たちに重くのしかかることも少なくありません。
成果が出ないと、自分を責めたり、周りと比較して落ち込んだりすることもあります。
そんな時代だからこそ、親鸞聖人の「他力」の思想は、私たちに大きな救いを与えてくれます。
この救いをまとめてみると、
- 自己肯定感の向上
- 不安やストレスからの解放
- 他者への寛容な心
以上の3つのポイントに絞ることができるでしょう。
具体的にみていきますね。
❶自己肯定感の向上
「他力」の教えは、「ありのままのあなたでいい」というメッセージを含んでいます。
私たちは、完璧な人間になる必要はありません。
煩悩を抱えたままで、弱さを持ったままで、阿弥陀如来は私たちを救うと願われているのです。
この事実を知ることで、私たちは自分自身の存在を肯定し、自己肯定感を高めることができるでしょう。
❷不安やストレスからの解放
すべてを自分の力でコントロールしようとすると、私たちは常に不安やストレスに苛まれます。
しかし、「他力」に身をゆだねることで、私たちはその重荷を下ろすことができます。
自分の力ではどうにもならないことは、無理に抱え込む必要はないのです。
阿弥陀如来の大きな慈悲に包まれているという安心感は、私たちの心を深く癒してくれるでしょう。
❸他者への寛容な心
自分が「他力」によって救われているということを知ると、他者に対しても寛容な心を持つことができます。
人間は誰もが不完全であり、煩悩を抱えていることを理解できるからです。
他者の過ちを責めるのではなく、共に支え合い、許し合うことの大切さに気づかされます。
これは、人間関係の悩みが多い現代において、非常に重要な視点と言えるでしょう。
「他力」を日々の生活に活かす3つの心構え


「他力」の思想を、どのようにして日々の生活に取り入れればよいのでしょうか。
それは、特別な修行をする必要はありません。
以下の3つのことを心がけてみると良いですよ。
1.「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と称えること
親鸞聖人は、「南無阿弥陀仏」と念仏を称えることを大切にされました。
この念仏は、自分の力で何かを達成するための行いではなく、阿弥陀如来への感謝の気持ちとして自然と口からこぼれ出るものです。
朝、目覚めたとき、ご飯を食べるとき、嬉しいとき、悲しいとき、いつでも心の中で「南無阿弥陀仏」と称えてみてください。
それは、阿弥陀如来の大きな慈悲とつながる瞬間となります。
2.自分の「愚かさ」に気づくこと
親鸞聖人は、自らを「愚禿(ぐとく)親鸞」と名乗られました。
これは、自分がいかに煩悩にまみれた愚かな凡夫であるかを自覚された証です。
自分の弱さや至らなさから目を背けるのではなく、それを素直に認めること。
そうすることで、私たちは阿弥陀如来の慈悲がいかにありがたいものであるかを、より深く感じることができるでしょう。
3.「おかげさま」の気持ちを大切にすること
私たちは、決して一人で生きているわけではありません。
家族、友人、職場の仲間、そして見知らぬ誰かの支えがあって、私たちは生きています。
日々の暮らしの中で、「おかげさま」という感謝の気持ちを意識してみてください。
この小さな心がけが、「他力」の思想をより身近なものにしてくれるはずです。
まとめ


親鸞聖人の「他力」の思想は、800年以上もの時を超えて、現代を生きる私たちに深く響く教えです。
さいごにザッとまとめますね。
- 自分の力だけではどうにもならないことがある
- 煩悩にまみれたどうしようもなく、不完全な存在である
- そんな私たちを、阿弥陀如来は決して見捨てることなく、そのままの姿で救い取ってくださる
この「他力」の思想は、私たちに心の平安と、他者への寛容な心をもたらします。
日々の生活の中で、「南無阿弥陀仏」と称え、自分の弱さを認め、「おかげさま」の気持ちを大切にすることで、私たちは親鸞聖人の智慧を実践することができるでしょう。
この激動の現代において、「他力」の教えは、私たち一人ひとりの心を温かく照らし、生きる力となってくれるはずです。
ぼくも、これからもこの教えを深く学び、みなさんと分かち合っていきたいと思っています。
さいごまでお読みいただき、本当にありがとうございました。

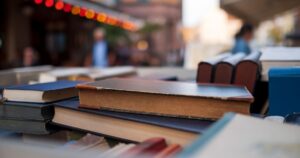





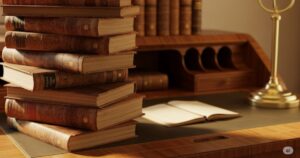

コメント